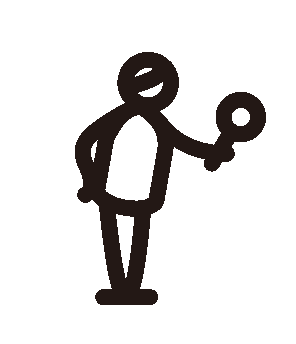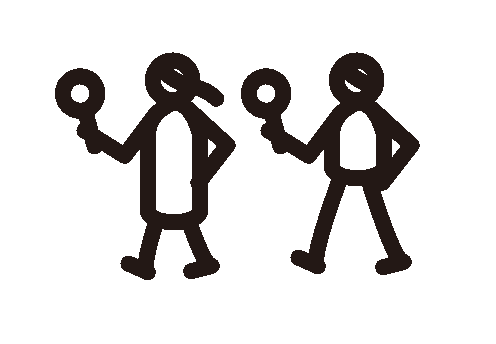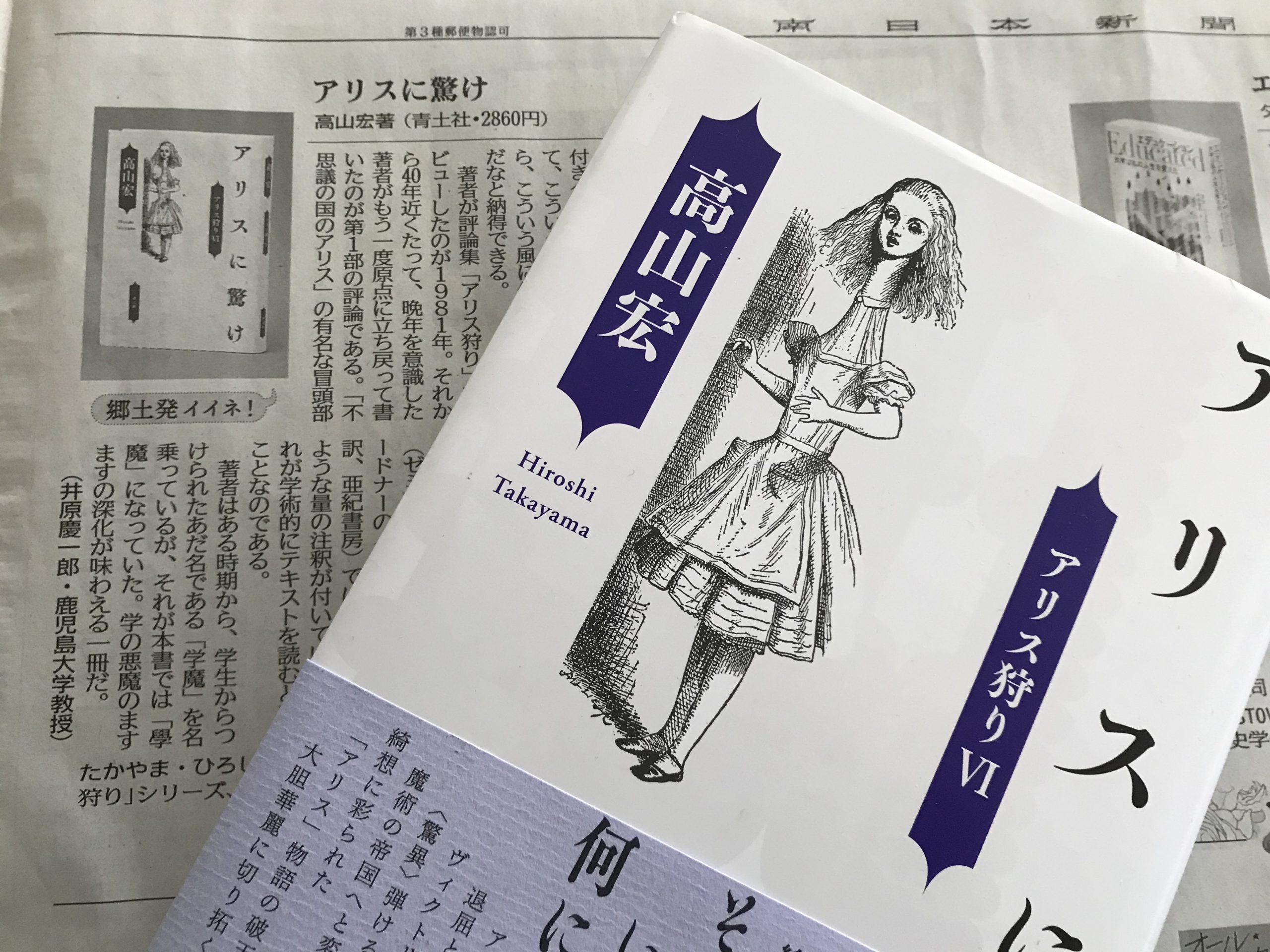私の研究の原点は、修士論文で取り組んだ「高齢女性の装いと自己表現」です。衣服や化粧といった装いは、単なる外見の問題ではなく、長い人生を通じて困難を乗り越え、自分らしさを保つ力になるのではないか――そう考えて始めた研究でした。これは、私自身が化粧品会社に勤務した経験から、どうしても取り組みたくなったテーマでした。
ケアスル介護コラム
人生の装い物語と自己表現――高齢女性の主観的ウェルビーイングを探る
このリンク先の内容は、2024年4月に「ケアスル介護」のウェブサイトに公開された一般向けの記事です。そこでは、装いが人生を支え、生きる力となることを語る2人の高齢女性の人生ストーリーが紹介されています。この生活史インタビューは1998年の夏に実施したもので、まさに昭和という時代を生き抜いてきた女性たちの語りです。個人の装いや自己表現は、同時にその時代の文化や価値観を映し出しているのです。
ただし、この記事に描かれているのはあくまで「装いがその人を支える場合」に限られています。中には全く衣服にこだわらない女性もいます。つまり、装いは一つの切り口にすぎないのです。
さらに、この装いの視点をそのまま高齢男性に当てはめることもできません。化粧や服装に関心を持つ男性は当時ごく少数派でした。そこで思い出されるのは、特養で出会ったある認知症の高齢男性です。かつて管理職を務めていた彼に介護職員が書類と印鑑を渡すと、突然表情が引き締まり、かつての自分を思い出すような姿を見せました。管理職としての役割は、まさに昭和の社会を背景に培われた習慣であり、その蓄積が認知症になっても呼び起こされたのです。その瞬間に生き生きとした表情が宿るのだと感じました。
では、過去の経験=生活史に眠っているものだけが、その人のQOL(生活の質)を高めるのでしょうか。ここで疑問が生じます。
長年農業を続けてきたある男性は、家族や介護職員から「畑に出れば生き生きするはず」と思われていました。ところが本人は「農作業は嫌いで、ようやくやめられると思っていたのに」と私にだけ打ち明けてくれました。本当に好きだったのは、むしろ政治や経済の話題。施設に入ってからテレビでニュースを見るようになり、そのときだけは目を輝かせ、生きがいを感じるのだと語ってくれたのです。ここには、昭和の労働観を背景としつつも、新しい環境で全く異なる喜びを見いだす姿がありました。
これらのエピソードが示しているのは、「その人らしさ」を過去の生活史だけに求める危うさです。義務感から続けてきたことと、心から好きで没頭してきたことは違います。そして、新しい環境での出会いが、その人にとって新たな喜びとなり、自我を躍動させることもあるのです。
つまり、「その人らしさ」は単純に生活史から自動的に導き出せるものではありません。過去と現在、そして新しい出会いとの相互作用のなかでこそ、その人らしさは形を取り戻し、生きる力につながっていくのだと思います。
この視点は、平成・令和を生きる若者たちにもつながります。たとえば大学生の就職活動でなされる自己分析も、過去の経験だけを振り返って「自分らしさ」を語ろうとすれば一面的になりがちです。人は年齢に関係なく、これまでの環境や習慣を意識的に変えることで新たな可能性を開くことができるのです。社会学ではこれを「コンティンジェンシー(偶発性・多様な可能性)」と呼びます。
この気づきこそ、私が研究を通して学び続けていることです。昭和から令和へと時代が移り変わっても、「その人らしさ」をめぐる問いは続いていきます。そしてここからまた、新たな問いが始まるのです。