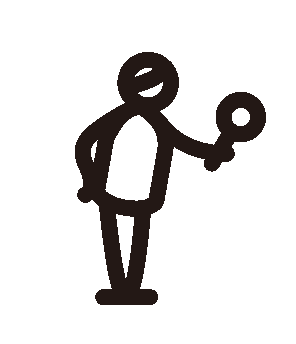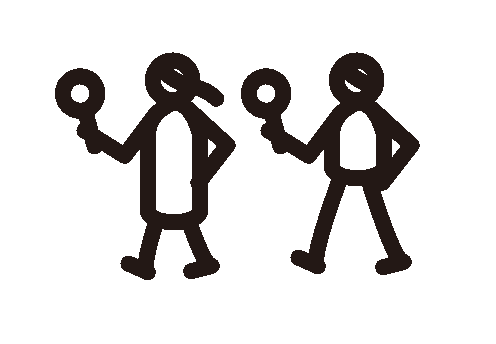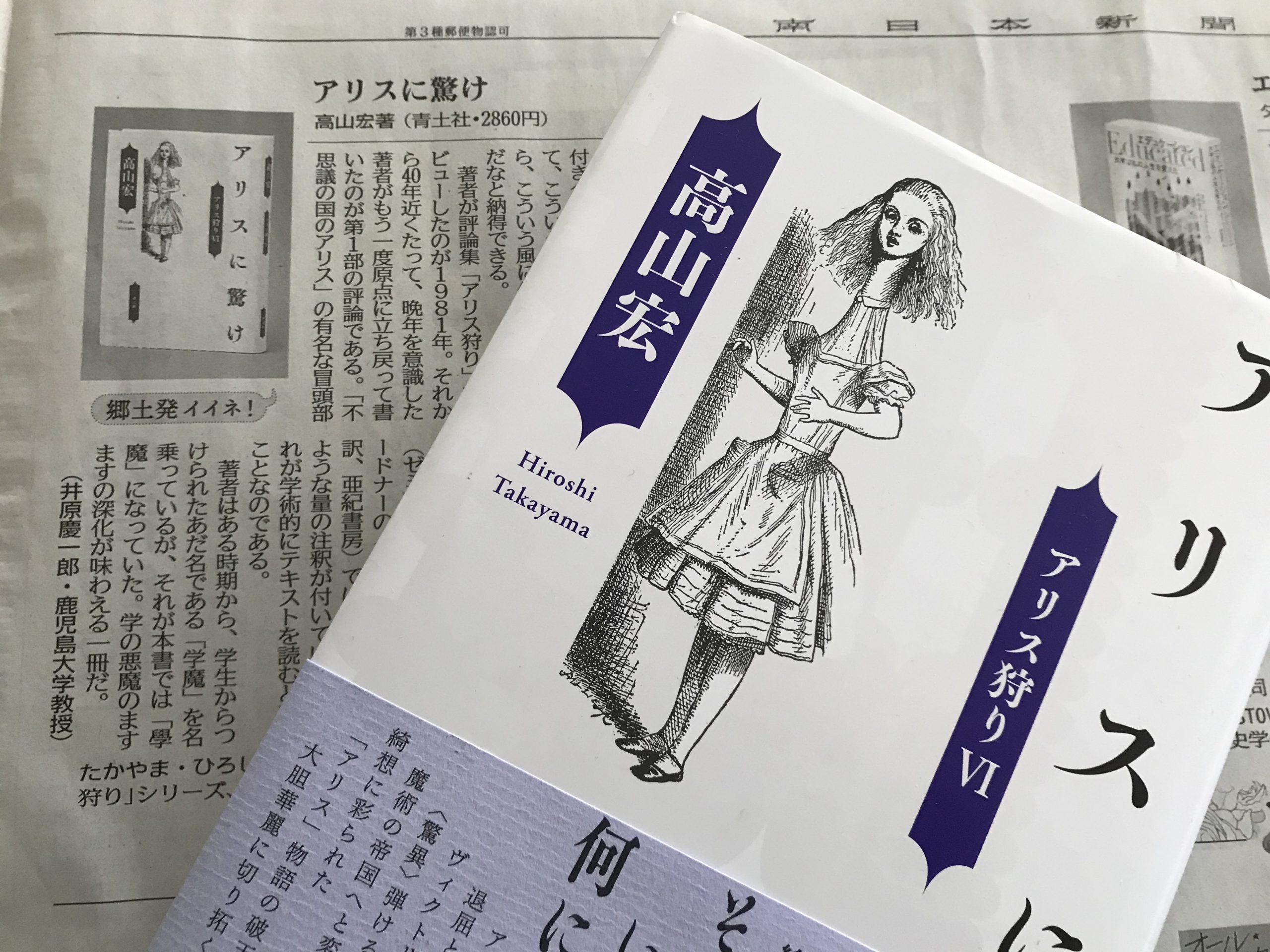「コトアミとは」からの続きの「コトアミについてもっと詳しく知る」のページです。
横断
「コトアミ」では、所属教員が自ら文章を綴り、投稿をしています。記事ごとにテイストが大きく異なるサイトになっていくでしょう。あまりにも広い分野で構成される我々の組織に関するブログの集合体、個性の一覧、個別の専門分野のアーカイブのように感じるかもしれません。しかし、ただモノゴトが並べられるのではなく、それらの繋がりが見えてくるようなサイトになっていくと思います。
記事には、その内容が一言で表された「タグ」が付いています。ぜひ「タグ」をクリックして下さい。類似の記事が一覧表示されますので、それら記事を辿ると、各々の活動やイベント・アイデアの間にある繋がりが可視化されていくと思います。今後も、タグは増えていき、投稿者によっては連載のような使い方をする場合もあるでしょう。記事が増えることで、繋がりがより一層可視化される、見る人の視点が横断していくことを目指しています。
また、「コトアミ」では、各研究者・教員・授業などの教育プロジェクトで得られた成果であるデータにもリンクして公開していきます。公開をするだけでなく、データを収集した背景にある動機や想いも含めて綴ることで、学問分野・産官学・地域・コミュニティなど、分野を越えて大学の知が活用されることを目指しています。本記事にも「データ公開」というタグを付けました。タグをクリックすると他の「データ公開」記事がソートされます。

個 to 網
ところで、「コトアミ」と見たり聞いたりしたら、どのような印象を受けるでしょうか。検索しても、「コトアミ」について教えてくれるウェブサイトは見つからないかもしれません。「コトアミ」は、鹿児島大学法文学部・大学院人文社会科学研究科の多面的な顔を伝えるために、私たちが考え出した造語です。
「コトアミ」は、「コト」+「アミ」という大きく分けると二つの要素からできています。「コト」は「言(葉)」と「(出来)事」に、「アミ」は「編むこと」「網」に通じており、「コトアミ」にはこれらの組み合わせから成る意味が重ね合わされ、圧縮されています。人文科学・社会科学・自然科学を問わず重要な言語、そして言語というネットワーク(網)、言語を編む=編集すること(辞書や本はその物質的な成果の最たるものでしょう)、出来事を繋ぐこと、繋いだ出来事がインフラとなってさらなる出来事を生み出していくこと(創発)。「タグ」というものや発想も、一種の編むことであり網を作ることでしょう。このウェブサイトで、法文学部・人文社会科学研究科での研究や知が動き出す気配を少しでも届けられれば幸いです。
「コトアミ」に関してもうひとつお伝えしておきたいのは、「アミ」ということばの持つ響きや響きから連想される事柄です。例えばフランス語で「アミ(ami.e.s)」といえば、「友人」や「愛好家」を意味します。大学という場所は「あたかも」外界から切り離されて、好きなことを探究することが──学生にとっても──求められ許される空き地のような場所であり、放課後のような時間です。専門的な用語を使えば、大学は現行に跋扈する効率性や合理性を一時的に括弧に入れることができる──立ち止まって検証し直すことができる──、時間的・空間的な「アジール(避難所)」なのです。そしてそうした知の探究は、成果としては個人によるものに見えたとしても、さまざまな水準で複数の人々の相互交流・交感・支援抜きには成立しません。こうした人々には現在生きている人たちに加え、過去に生きた人たち──先行研究──、そして成果が受け渡される未来の人たちが含まれます。こうした意味で「コトアミ」とは、大学の(社会や人々にとって)あるべき基本的な姿勢や性格、そして理念を示すものでもあります。
ここまで読んでくださった「あなた」も、もう「コトアミ」のノードかもしれません…