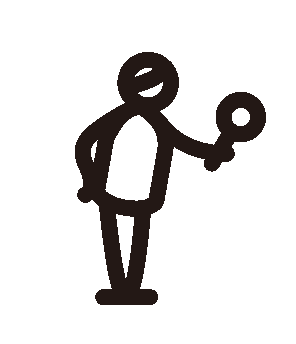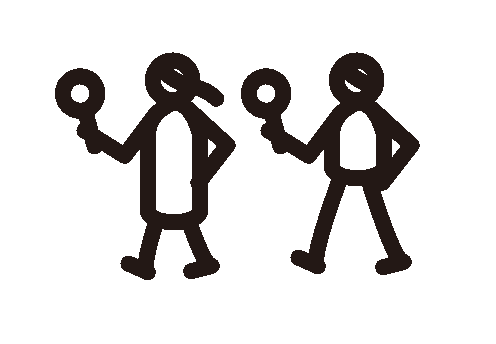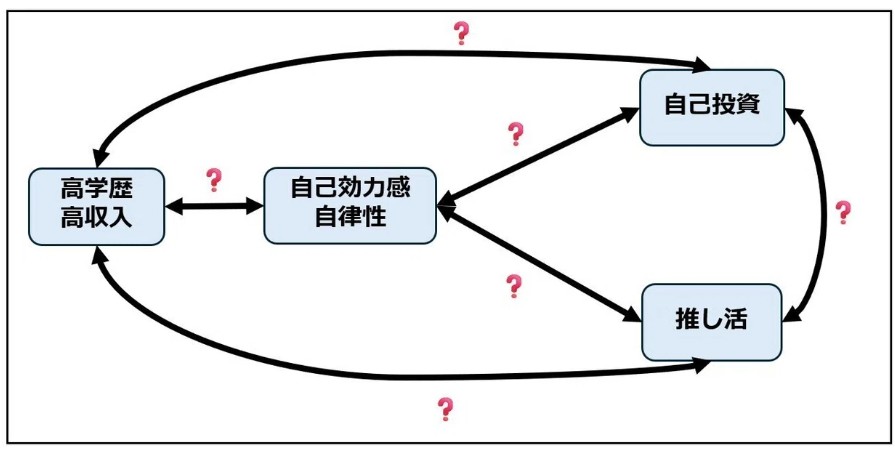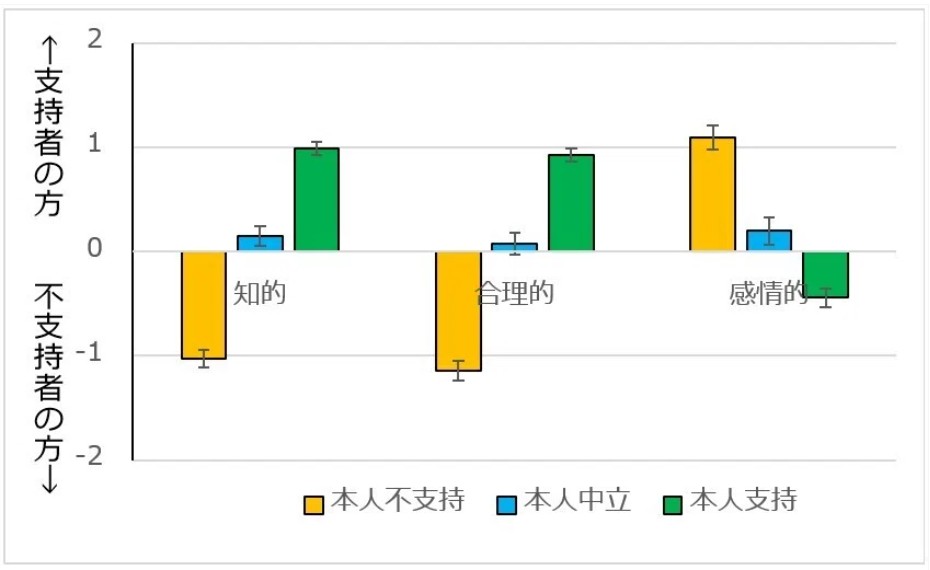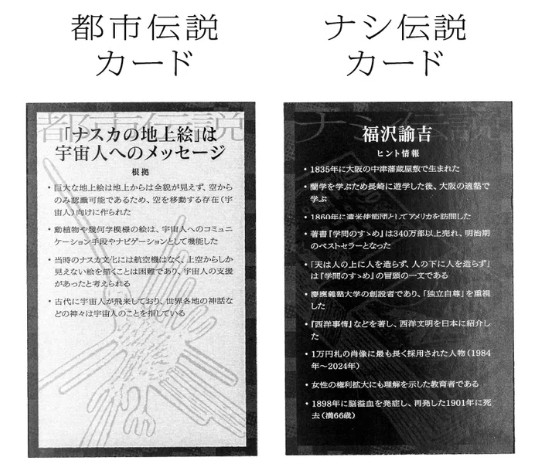noteで「パフォーマーとしてのディケンズ: ディケンズの公開朗読について」を公開しました。この記事は、『ドクター・マリゴールド 朗読小説傑作選』(井原慶一郎編訳、幻戯書房、2019年)所収の「訳者解題」をもとに要約・再構成したものです。詳細は以下をご覧ください。
チャールズ・ディケンズの公開朗読は、1853年の慈善活動として始まり、作家人生の後半における主要な活動へと発展した。プロの朗読家への転向は、経済的必要性、家庭内の不和から生じる精神的苦痛の解消、そして何よりも読者との直接的で「愛情のこもった」関係を求める強い渇望という、複合的な動機によって推進された。
ディケンズは自作を「省略」する手法で朗読台本を作成し、特注の舞台装置と、声色、表情、ジェスチャーを駆使した卓越したパフォーマンスを組み合わせることで、印刷されたテキストに「立体写真」のような生命を吹き込んだ。この活動は商業的に成功を収め、ロンドン、イギリス地方都市、アメリカで常に満員の聴衆を魅了し、彼が遺した総資産の約半分に相当する約4万5千ポンドの収益をもたらした。
しかし、その成功は過労による健康の悪化という大きな代償を伴い、最終的にはドクターストップによってキャリアの終焉を迎える。彼の公開朗読は、作家が自らの作品を声で体現し、読者との間に他に類を見ない親密な関係を築き上げた、文学史におけるユニークな試みであった。