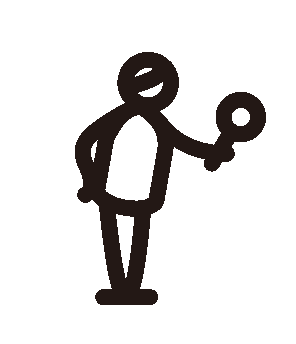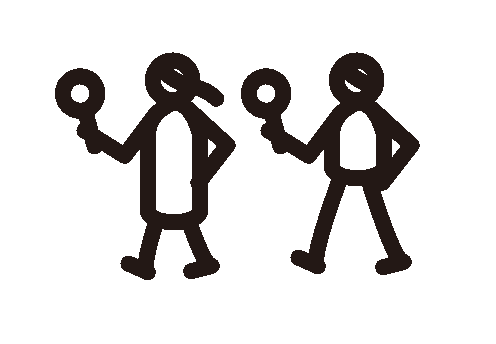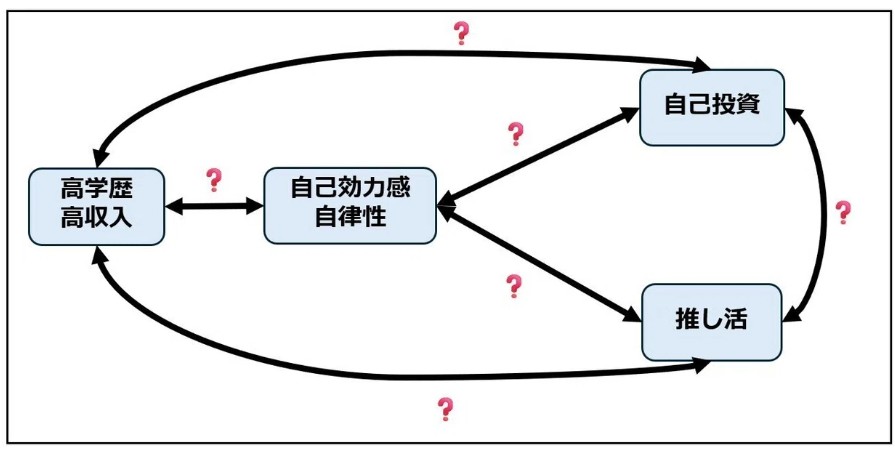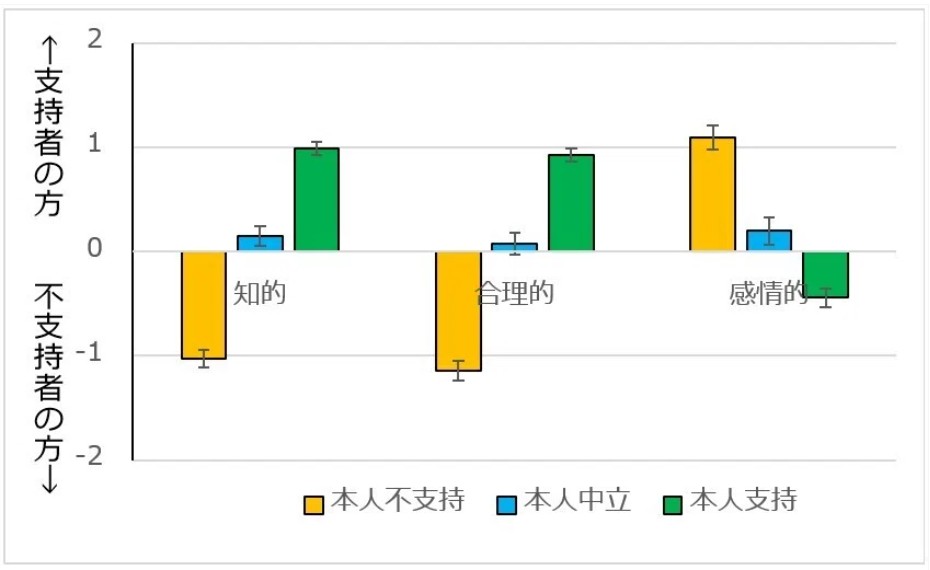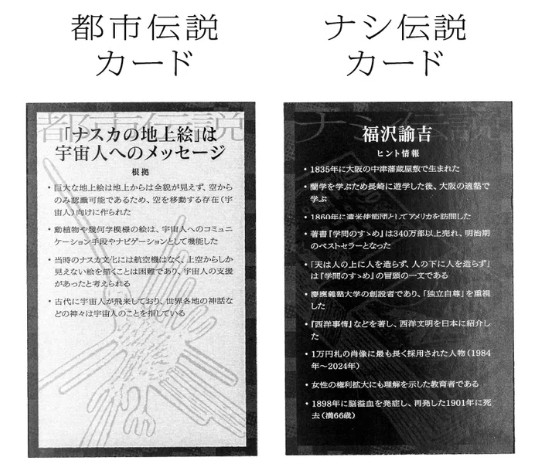加藤幹郎監修、杉野健太郎編、映画学叢書『映画とイデオロギー』ミネルヴァ書房、2015年
第4章 Shall weリメイク?──『Shall weダンス?』とハリウッド映画のイデオロギー
本章が扱うのは、映画のなかのイデオロギー*というよりも、むしろイデオロギーとしての映画――イデオロギー的実践としてのリメイク――である。本章では、ハリウッドによってリメイクされた外国映画のひとつの事例として『Shall we ダンス?』(周防正行監督、1996年)を取り上げ、それが〈アメリカ化*〉された過程を詳細に見ていく。本章の目的は、ハリウッド映画産業というブラックボックスのなかでおこなわれた〈アメリカ化〉のプロセスを具体的に明らかにすることであり、ハリウッドが外国映画をリメイクするという行為それ自体のなかに〈ハリウッド映画のイデオロギー〉を読み取ることである。
オリジナル版『Shall we ダンス?』は、脚本の構成その他においてすでにある程度〈アメリカ化〉されていたが、1950年代の〈古き良きハリウッド映画〉のスタイルを参照した日本映画『Shall we ダンス?』は、2000年代のハリウッド製アメリカ映画である『Shall we Dance?』(ピーター・チェルソム監督、2004年)と比べて、撮影・編集方法(カヴァレッジ*、コンティニュイティの強化*)、物語の展開のペースの速さ、アメリカ文化のイデオロギーの強化などの点で大きく異なっていた。アメリカ流の娯楽映画を目指した周防の『Shall we ダンス?』は、もちろん商業主義とは無縁ではないが、その周防の映画作りの作家主義*的な側面が際立つほどに、リメイク版『Shall we Dance?』は、スターの起用、テスト・スクリーニング*、若年層の取り込みなど徹底した商業主義に貫かれていた。こうしたマーケティング重視の映画作りやコスト削減・資金調達のための方策(国外製作*、プロダクト・プレイスメント*)は、映画テクストに直接的な影響を及ぼしている。オリジナル版の約10倍の予算をかけて製作されたリメイク版『Shall we Dance?』は、宣伝・配給面での圧倒的な優位を背景として、全世界でオリジナル以上の興行収入を得たが、その一方で、アメリカにおいてオリジナルを越える評価を得ることができなかった。興行収入と作品の完成度や評価は別問題であると言えばそれまでだが、これはハリウッド映画が抱える構造的問題の表れと言えよう。本章はひとつの事例研究であり、一外国映画のリメイクにおける〈アメリカ化〉のプロセスを明らかにしたにすぎないが、このリメイク論=イデオロギー論の枠組みは、ハリウッド映画産業のグローバルな〈ヘゲモニー*〉を考察するうえで、有効な手がかりを与えてくれるはずである。
用語集
- イデオロギー……社会や文化における支配的な価値観や信念体系。ここでは、ハリウッド中心の思考様式を指す。
- アメリカ化……異文化の作品や要素が、アメリカの価値観・様式・市場に合わせて変えられること。映画では、登場人物やテーマ、演出がアメリカ的に改変されることを指す。
- カヴァレッジ……同じシーンを複数の角度・距離・構図で撮影し、編集時に自在に組み合わせられるようにする手法。
- 強化されたコンティニュイティ……現代のアメリカ主流映画に見られる形式的特徴で、古典的ハリウッド映画のコンティニュイティ・システムが強化されたもの(デヴィッド・ボードウェルによる命名)。コンティニュイティとは、観客が場面の連続性や空間関係を自然に理解できるように編集・撮影を行う技法のことであり、ショットの切り替えにおいても視線や動作の方向、空間配置などが一貫して保たれるように配慮される。強化されたコンティニュイティの特徴として、編集の速さ、望遠レンズと広角レンズの組み合わせによる撮影、近接フレーミング、頻繁に動くカメラが挙げられる。
- 作家主義……映画を監督の芸術作品ととらえ、その個性やビジョンを重視する考え方。
- テスト・スクリーニング……映画完成前に観客を対象におこなわれる試写。アンケート結果に基づいて、再編集や撮り直し、場合によっては結末が変更されることもある。
- 国外製作……コスト削減や税制優遇などを目的に、映画をアメリカ以外の国で撮影・製作すること。シカゴの舞台設定にもかかわらず、『Shall we Dance?』のほとんどの撮影はカナダのウィニペグでおこなわれた。
- プロダクト・プレイスメント……映画製作者がスポンサー企業のロゴや製品を画面に登場させること。スポンサーは、その見返りとして資金や製品やサービスを提供し、映画とタイアップした宣伝活動をおこなう。
- ヘゲモニー……文化的・経済的な優位性によって他者を支配・主導する力。ここではハリウッド映画産業が世界映画市場において持つ主導的地位を意味する。
後記(2025年から振り返って)
この論文が2015年に描いた「ハリウッドによるリメイク=〈アメリカ化〉」という構造は、現在においても一定の影響力を持ち続けています。ただし、この10年の間に映画産業のグローバル地図は大きく書き換えられました。とりわけ中国市場の急成長により、かつてアメリカ映画の主要な海外市場であった日本の地位は相対的に低下し、ハリウッドのリメイク戦略やマーケティングの焦点も変化を余儀なくされています。
一方で、Netflixをはじめとするストリーミング・プラットフォームの拡充によって、劇場公開やリメイクといった旧来の枠組みに依存せず、オリジナル作品をそのまま世界に届ける新たな回路が開かれました。字幕や吹き替えによる多言語展開によって、非英語作品が国境を越えて広く視聴されるようになり、ローカルな文化的特徴を保持したままグローバルな人気を獲得する事例も見られます。こうした配信モデルは、リメイクを“翻訳”の手段とするこれまでの構図を揺るがすものだと言えるでしょう。
また、劇場流通においても新たな動きが見られます。その象徴的な事例が、2023年に公開された『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)です。日本語オリジナルのまま北米で広く上映され、興行的にも成功を収めたこの作品は、日本映画が〈アメリカ化〉を経ずに受容される可能性を示しました。配信と劇場、それぞれの領域で「非リメイク」的な成功事例が現れていることは、ハリウッド映画の一極支配が揺らぎつつある兆候とも受け取ることができます。
中田秀夫監督『ハリウッド監督学入門』(2009年)は、2000年代のハリウッド映画の製作の裏側を知るうえで参考になる重要なサブテキストです。
ミネルヴァ書房
映画とイデオロギー