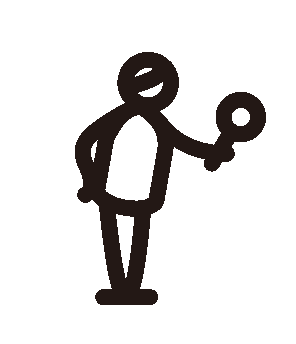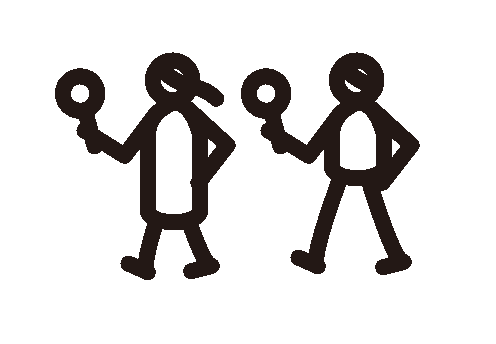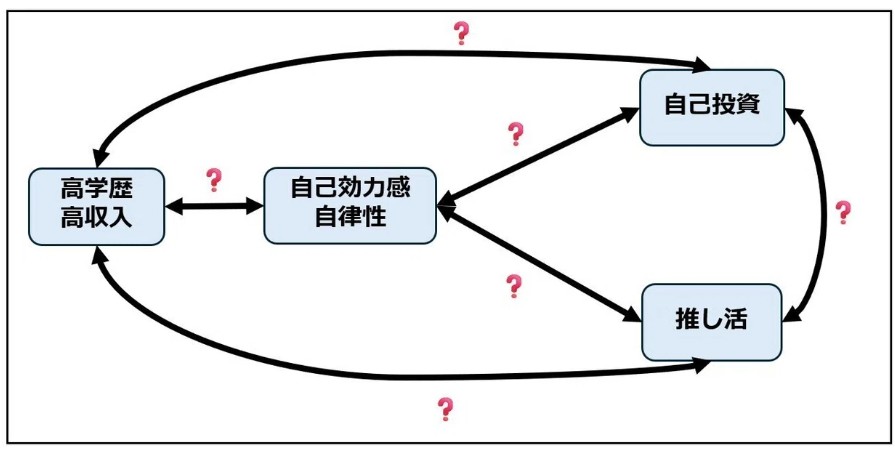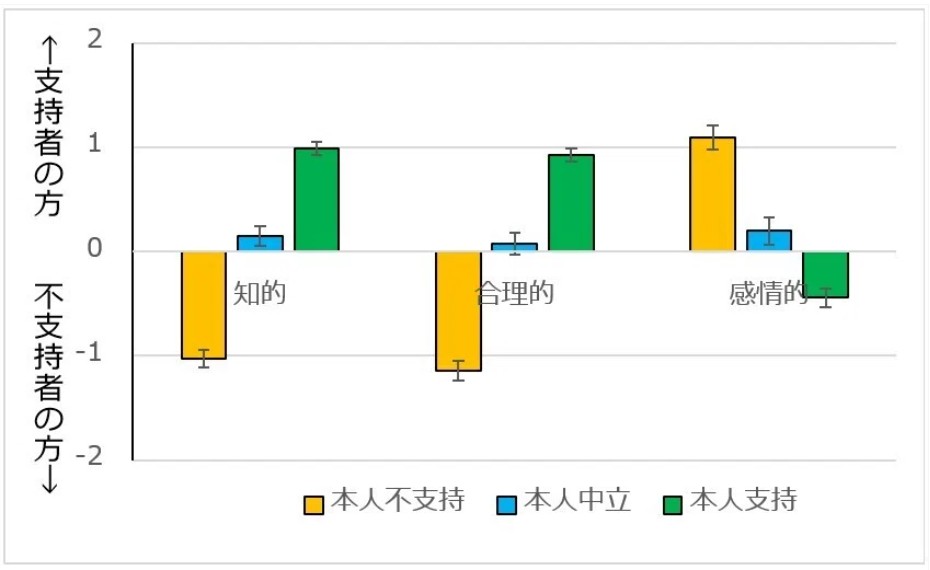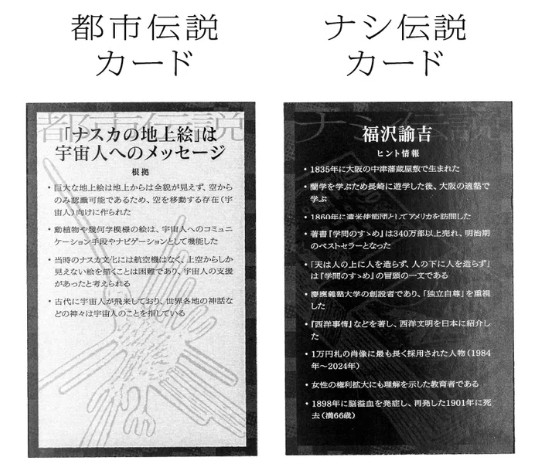アン・フリードバーグの二冊の主著を翻訳した経緯については、日本映画学会会報(2012年12月)に書いたエッセイをご覧ください。
ここで述べたように、「邦訳『ウィンドウ・ショッピング』(2008)出版以前、フリードバーグは日本の一般の読者にはほとんど知られていない存在」でした。しかし、現在はインターネットで検索すると、多くの記事やブログ等で言及されているのが確認できます。何よりも驚いたのは、2023年度の大学入学共通テストの「国語」の問題にアン・フリードバーグが引用されたことです。
窓はフレームであるとともに、プロセニアム〔舞台と客席を区切る額縁状の部分〕でもある。窓の縁〔エッジ〕が、風景を切り取る。窓は外界を二次元の平面へと変える。つまり、窓はスクリーンとなる。窓と同様に、スクリーンは平面であると同時にフレーム――映像〔イメージ 〕が投影される反射面であり、視界を制限するフレーム――でもある。スクリーンは建築のひとつの構成要素であり、新しいやり方で、壁の通風を演出する。
現代文の問題になったのは、柏木博氏の『視覚の生命力――イメージの復権』(岩波書店、2017年)なのですが、フリードバーグの『ヴァーチャル・ウィンドウ』冒頭を引用した箇所が出題されたことで、多くの受験生の眼に触れることになりました。問題文に付いた注には「アン・フリードバーグ――アメリカの映像メディア研究者(一九五二―二〇〇九)」とあります。
邦訳『ウィンドウ・ショッピング』と『ヴァーチャル・ウィンドウ』は、ひとえに原著の素晴らしさゆえに多くの新聞・雑誌の書評で取り上げられました。詳しくは下記をご覧ください。
note
共訳書『ウィンドウ・ショッピング』
note
共訳書『ヴァーチャル・ウィンドウ』
特に劇作家・評論家の山崎正和氏(1934-2020)は『ウィンドウ・ショッピング』に続いて、『ヴァーチャル・ウィンドウ』についても『毎日新聞』に長編書評を書いてくださり、そのいずれもが書評集『「厭書家」の本棚』(潮出版社、2015年)に再録されています。
また、『日本経済新聞』に掲載された原克氏(早稲田大学教授)による『ヴァーチャル・ウィンドウ』評は、ネットで全文を読むことができます。
日本経済新聞(2012年8月26日)
ヴァーチャル・ウィンドウ アン・フリードバーグ著 世界認識への影響あぶり出す
さらに、『ヴァーチャル・ウィンドウ』は東京国立近代美術館で開催された「窓展:窓をめぐるアートと建築の旅」(2019.11.1–2020.2.2)において主要参考文献として紹介され、キュレーションや展示のコンセプトにも影響を与えることで、アカデミズムに留まらない広がりを見せました。
最後に、『ヴァーチャル・ウィンドウ』について語るアン・フリードバーグの映像(英語・字幕なし)を紹介します。
トランスクリプトと訳はこちらをご覧ください。